今回の記事では、棒編みの記号で v はどう編む?一度で覚えるシリーズ【v編】をご紹介していきます。
記号の『v』はどんな名前の記号なのか、どんな編み方をするのか詳しく見ていきましょう。
かぎ編みをしている方だと、「こま編みかな?」と思われる場合もありますが、棒針編みでは全く別な記号の意味になりますので、注意しましょう。
この記事では、この『v』について、わかりやすく説明して、一度で覚えられるようご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
棒編みの記号で v は?どうするの?

さっそく本題ですが、この『v』という記号は、棒針編みでは『すべり目』といいます。
すべり目は、言葉の通り、編まずに目をすべらすように移動するだけなので、とっても簡単な編み方です。
記号が下記の画像になります。

滑り目にも表目と裏目の編み方がありますので、注意しましょう。
では、この滑り目はどんな場面で、利用するといいのでしょうか。
次で簡単にご紹介していきます。
どんなところで使うの?

あなたは、どんなところですべり目を利用すると思いますか?
意外と滑り目いろいろな場面で利用することが多い編み方で、わたしが最も使ったのは、靴下を編むときのかかと部分です。
子のかかと部分では、滑り目と掛け目を繰り返して、目を減らしたりしたりと少し高度な編み方ではありましたが、とても楽しい編み方になりました。
これが自分が作った子供用の靴下です。(別の記事でもご紹介しています。)

参考にした本は、下記になりますので、ぜひお試しください。
このほかにも、滑り目の効果として、メリヤス編みなどを編むと、どうしても端が丸くなってしまいます。
最後のアイロンの仕上げで収まりますが、編んでいる最中から丸くなってしまうと、大変編みづらかったり、サイズを測りながら編みたいのに丸まってうまく図れなかったりしますが、これを解消するのにもすべり目が役に立ちます。
それは、すべり目を端で編むだけです。
すべり目を端で編むだけでなんと、メリヤス編みを編んでも、丸くならないんです。
どんな感じで編めばいいのか、次でご紹介していきます。
編み方はこちら!

それでは、すべり目の編み方を次の編み図の通りに編みながらご紹介してきます。
前述で説明した通り、端で編む編み方で編んでいきますので、編み図はこちらです。

両端のそれぞれ9か所のすべり目ができるように編み図を作成してみました。
このように端で編むことによってどのような効果があるのか、作りながら見ていきましょう。
では、編んでいきます。
1、作り目を20目作ります。

2、2段目裏側から見ながら、最初の段のすべり目を行います。
糸は手前に持ってきながら、1目目の目をそのまま右の針に移し、すべり目ができました。
 ↓
↓

3、2目目からは編み図通りに表目編み(裏から見ているので、裏目編み)していきます。

4、反対側の端も同じようになにも編まずに右の針に編み終わります。
これで、2段目が完成しました。

↓

5、3段目は表を見ながら編みます。
3段目は何もせず、端も普通に表目編みをします。

↓

↓
反対側も普通に表目編みをします。

5、3段目が編み終わりました。

6、これを繰り返していきます。
完成しました。

出来上がりなので、上と下がくるんとなっていまして申し訳ございません。(汗)
こう見てみても、端ですべり目をすることによって、くるまっていないことがわかります。
通常に表目編みをするとくるまってしまうところをすべり目をすることで、それを防いでくれるという効果があります。
見た目もそれほど、変わりませんのでぜひお試しください。
すべり目は、大体が2段で、一つのすべり目ができるようになっています。
そうすると、記号の下ですべりをするのか、上ですべり目をすればいいかわからなくなります。
わたしも、しっかりすべり目をやろうと思ったら、どっちなんだ?疑問がわいてきて、こんがらがりました。(笑)
なので、しっかりどこですべり目をするのか覚えておきましょう。
すべり目は記号のどこでするの?

先ほど、手順をご紹介しておりますので、大体は、どこでするのか見当がつくかとは思いますが、すばり、記号の下の段ですべり目を行います。
その上は、普通に編み、2目合わせてすべり目を完成させるような形です。
考え方は、『記号の1番下ですべり目』と覚えておけば初心者でも久々に編む方もわかりやすいかと思いますので、ぜひ覚えてみてくださいね。
編み方を覚えて編み物を楽しもう
この記事では、棒編みの記号で v はどう編む?一度で覚えるシリーズ【v編】をご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。
意気込んでみてみたけれど、なんだただそのまま編まないだけなのか!と拍子抜けかもしれません。(笑)
だけど、これもちゃんとした編み方ですし、特にわたしは靴下にはまったので、かかとを編むときによく使う記号でした。
今では何とかかかとを編めるようにはなりましたが、最初は全然編めなくてかかとを編むだけでも1週間かかりました。(大変でした。(笑))
ただ、できたときには感動して、また編みたいなと思うようになりました。
ぜひあなたにもその体験を一緒に味わってほしいなと思いますので、ぜひ挑戦してみてくださいね。





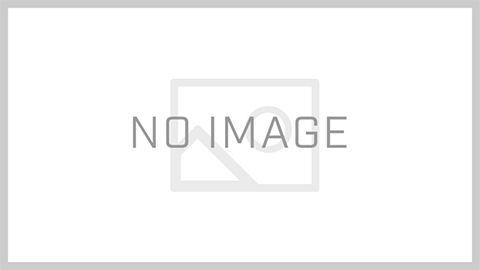



コメントを投稿するにはログインしてください。